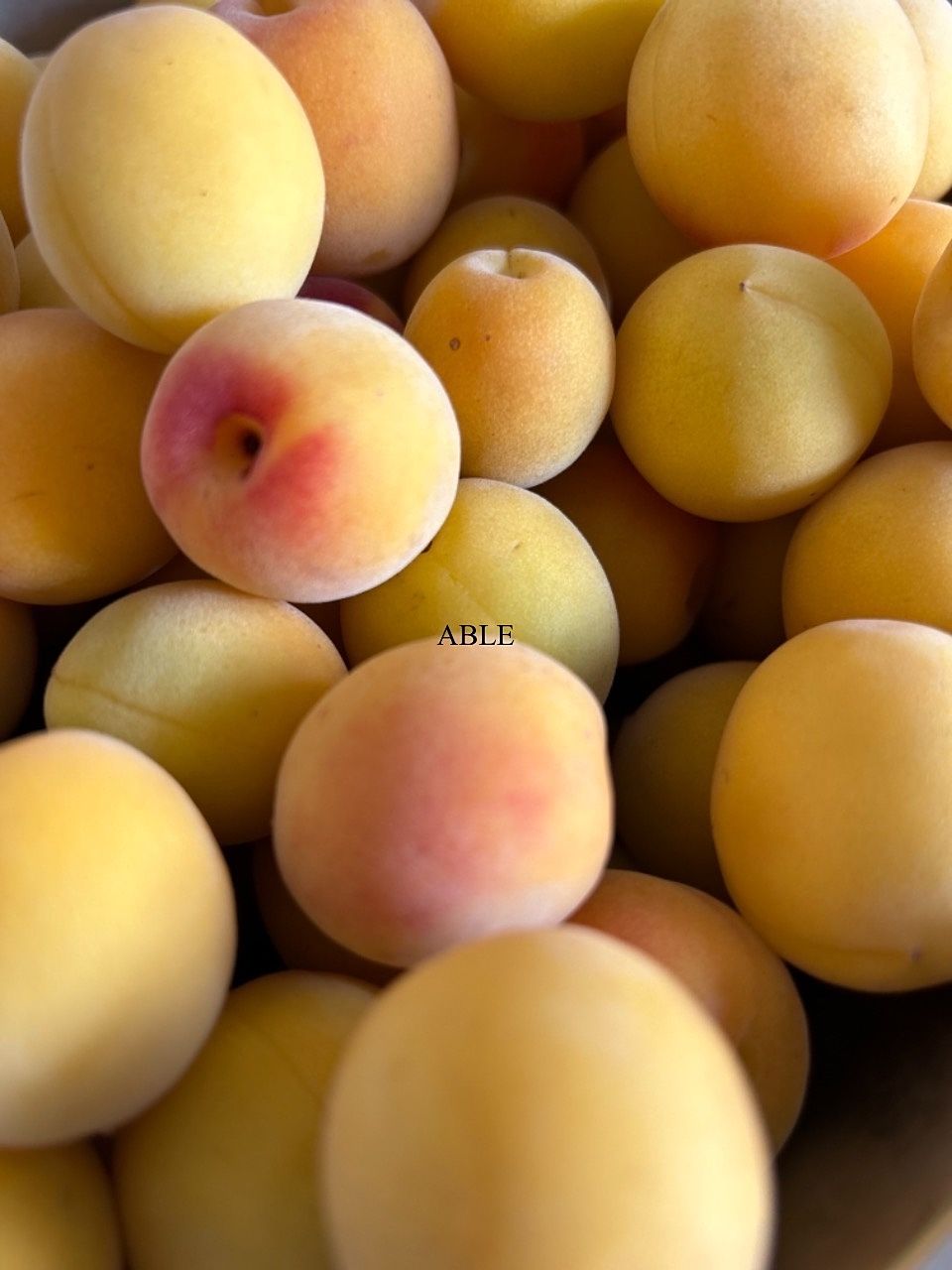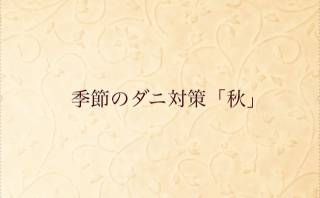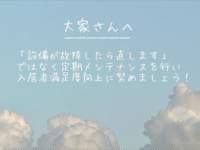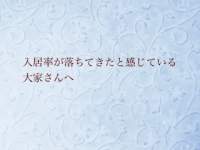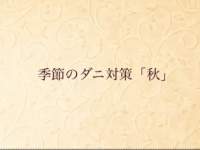『梅はその日の難逃れ』
今年は自家製の白梅干しをつくりました!「すっぱくて、しょっぱい」昔ながらの梅干しです。
梅干しの歌
調べによると、「梅干しの歌」は1910年(明治43年)発行の『尋常小学校読本 巻五』で発表された七五調の韻文。
梅の木に花が咲き実が成り、漬けられて梅干しになるまでを描写しています。
当時はメロディが付けられてなかったそうです。(世界の民謡・童謡より引用)
私が今回梅干しを漬けてみようと思ったきっかけは、祖母の口ずさんでいた歌を思い出したからです。(手遊び歌でした)
梅干しという身近にある食べ物の人生を歌ったこの曲は、今となっては梅干しを食べるたびに思い出します♪
歌詞
二月三月花ざかり、
うぐいす鳴いた春の日の
たのしい時もゆめのうち。
五月六月実がなれば、
枝からふるいおとされて、
きんじょの町へ持ち出され、
何升何合はかり売り。
もとよりすっぱいこのからだ、
塩につかってからくなり、
しそにそまって赤くなり、
七月八月あついころ、
三日三ばんの土用ぼし、
思えばつらいことばかり、
それもよのため、人のため。
しわはよってもわかい気で、
小さい君らのなかま入り、
うんどう会にもついて行く。
ましていくさのその時は、
なくてはならぬこのわたし。
(繰り返し)
....................................................
いかがでしょうか?
なんとなく「梅干し」に親近感がわく歌詞ですね。
祖母から「手遊び歌」として教わりました。
その昔、小学生の子どもたちが楽しく歌っていた光景が浮かんできて…今の子供達にも伝われば良いなあと思いました。
調べると歌詞や曲が変更されながらも、みんなのうたで「ウメボシジンセイ」として放送されたそうですし、他では「梅干し体操」もあるそうで、今でもこの歌が存在して嬉しいです。♪
梅はその日の難逃れ
このことわざは、昔旅人がその土地特有の熱病や風土病にかからないように、梅干しを食べていたことに由来するそうです。
平安時代の頃から万能薬としての梅干し。
保存性もあり、持ち歩けるのでとても重要なものとして扱われてきたようです。
「梅干し」の歴史をたどると梅干し作りは少し手間がかかりますが、面倒なこととは思わなくなりました。
「梅はその日の難逃れ」とは
梅干しを朝に食べておけば、いろいろな意味で多少の難を逃れることができるということ。
とても体に良さそう!
良いそうです。
暑い今時期の熱中症対策にも。
昔ながらの白梅干し。(シソには漬けない梅干しです)
味見をしたら…すごく、しょっぱい、すっぱい!
毎日、食べようと思います。
関連した記事を読む
- 2024/09/20
- 2024/09/10
- 2024/09/03
- 2024/08/23